2023.06.27
谷口広樹さんを巡る対談その1
~対談 津々井 良、伊藤桂司2021.11.10~
(聞き手)小池アミイゴ (編集)伊藤万里
訃報に触れ
小池)本日は、よろしくお願いいたします。 2021年の8月に、「谷口広樹さんが急逝された」と連絡があったときに、本当にショックで言葉が出なかったんです。 ボク自身のことをいえば、「TIS(東京イラストレーターズ・ソサイエティ)」に長年関わらせて頂いて、マイペースで生きて来た人間なんです。しかし、自分と同世代あるいは若い人たちが亡くなる度に、「一人のイラストレーターが、この世からあっさりといなくなってしまった」という悔しい思いが根底にありました。特に谷口さんぐらい幅広くご活躍され、我々の記憶に確かに残っている方のことは、やはり記録として残しておかなければいけないと思っています。
ボクは、谷口さんが「第4回日本グラフィック展」(1983年)を受賞された頃、セツ・モードセミナーで絵を学び始めました。その頃のセツの生徒たちは谷口さんの作品からもの凄く影響を受けていたんです。具体的には、谷口さんの作品をマネて絵の中に点、点、点と描くのが流行っていましたし、絵の構図に関しても、日比野克彦さんよりも谷口さんの影響が大きかったイメージがあります。谷口さんは当時から非常に印象深い存在だったんです。
まあ、僕の話はこれくらいにして、おふたりの谷口さんに対する思い出などを語って頂けたらと思います。

伊藤)8月30日にTIS事務局スタッフからご連絡を頂いて、「谷口君が北海道の大学で倒れたようなんですが、ご家族の電話番号をご存じでしょうか?」と聞かれたんです。すぐに谷口君を招へいした大西洋さんの連絡先をTIS事務局スタッフから聞いて電話してみたところ、彼もかなり動揺していて、「今、病院にいるんですが、こちらに大動脈解離で運び込まれた時点で、もう助からないかもしれないと病院から宣告を受けました」と説明してくれました。実は、家族と連絡を取りたいと言われたのは、病院側として「いつまで延命措置をすべきか」という判断を仰ぎたいという意味で、この時点で、かなり重篤な状態だったようです。
そのような経緯を聞いた途端に、動揺して手が震えて、何が起こったのか呆然としてしまって、まるで自分が自分でないような気がしていました。その間に、うちの奥さんがいろいろと調べてくれたんで、ようやく、あちこちに連絡できたんですよ。
津々井)僕の方には8月30日に、古くからの友人の「うんちマン」こと小関昭彦さんから、「谷口さんが倒れた」という連絡があったんです。ところが、この彼は日頃から、ちょっと悪ふざけが過ぎるタイプなので、てっきり「からかわれているのかな」と思っていたんですよ。何しろ、谷口さん自身が「自分は90、100歳まで生きて、ずっと絵を描いていきたい」と会う度に話していたくらい、常に描くことしか頭にないような人だったんです。
大学の方もあと一年くらいで退職というタイミングだったので、よく「学校を辞めた後は、どうするんだ?」と尋ねると、「90、100歳になっても、ずっと絵を描いていきたい。もしかしたら、近い将来、東京を離れて地方で活動してもいいかな」とか、そんな具体的な夢まで語っていたんですよ。
伊藤)共通の知人に、九州の熊本の地域活性化の仕事をしている人がいるんですが、谷口君はその彼ともよく会っていて、向こうでの仕事も引き受けていたし「熊本に住むのも悪くないなあ」と話していました。
小池)谷口さんの最期の言葉に触れたのはお亡くなりになる前日のこと、個展を開催されている西荻の「ヨロコビtoギャラリー」からSNSで「コロナの影響で例年よりもお客様が少ないから、これからのことを考えようか」ということを呟かれていて、その言葉が妙に胸に突き刺さったんですよ。
伊藤)どうしても、関連づけて考えてしまいます。 これまでずっと継続的に絵を描いてきて、本当だったら、今のままの勢いで更に活動を広げて行く筈だったんですよね。何しろ、西荻での個展の開催と同じ9月に、銀座の「コバヤシ画廊」でも新作の発表を控えていたのですからね。
作品
小池)伊藤さんとの二人展の計画もあったんでしょうか?伊藤)いや、具体的な話はこれからだったんですが、遥か昔80年代に、二人展はやったことがあります。
津々井)谷口君とヒロ杉山とで、「ギンザ・グラフィック・ギャラリー」で三人展をやったのはいつだったかな?
伊藤)三人展は、2004年でした。具体的に二人展の話は出ていませんでしたが、「一緒に何かやりたいね」ということはよく言い合っていました。
小池)これまでのお二人の作風を見ていくと、谷口さんと伊藤さんはどこの部分で引き合うのかなという気持ちがあって、そこが非常に興味深いんですよね。
伊藤)うん、たしかに、作風は全然違いますよね。
小池)谷口さんが倒れた時に、伊藤さんがすぐにお電話を下さって、「ああ、それだけ心配されているんだ」と実感させられました。そういった「モノづくり」をする同士としての絆について語っていただけますか?
伊藤)まあ、僕は谷口君ほど真摯かどうか分かりませんが、「モノづくり」に対しての姿勢については通じあう部分がありました。谷口君とは絵のベクトルは違っていますが、根源的には近しい部分があったような気がしています。お互いに、結構、非日常的というかね。
津々井)要は、現世でないところで描いているんだよね。
伊藤)そうですね。
津々井)ロンちゃん(伊藤さん)の方はパースがある絵を描いていくんですが、谷口君の方はどちらかというとパースがない作品ばかりで、絵本なんか描いていても、どこかうねっていて作品がレイヤーになっているんですよ。そんな風に、二人の作風は全く異なっているんですが、表現しているものは、どちらも天国とは言わないけれど現世ではない感じなんですよね。何か、そういった精神的なものを大事にしているという印象を受けるんです。
伊藤)谷口君とは、年を重ねるごとに、いわゆる精神世界や異世界の話をよくしていましたね。 2人の間では、他にも美術や音楽で作品を創る上での多くの共通項があったと思います。
津々井)ロンちゃんは、時代の変遷とともに、すごく画風が変わって行きましたよね。
伊藤)僕はどんどん画風が変わったけれど、谷口君には安定した軸があって、思えば、初期のころから多様性もありましたよね。彼の場合は作品が変化するというより、どんどん世界が拡張していくような感じでした。

道元
※掲載作品と対談内容は必ずしも一致しておりません。ご了承下さい。
アート雑誌「PORTFOLIO」
津々井)たとえば、1992年発刊のアート雑誌の「PORTFOLIO」に掲載された谷口君と榎本了壱さん、長友啓典さんによる三者対談を読んでいても、谷口さんはあの頃と少しも変わっていないんですよね。伊藤)この「PORTFORIO」の中で、彼は神羅万象を描いていますね。
津々井)谷口君は、「これからも自分は生きて行く」という視点で、ファインアートみたいなものを表現していましたが、当時は、イラストレーションそのものが半分アートというような感じで呼ばれていました。改めて、谷口君が「第4回日本グラフィック展」を受賞した時の言葉を読み返してみると、「アートの方向に進んで行くと面白くないから、あくまでもイラストレーションの方向で、何かアートっぽいことをやりたい」と発言していたんです。実際に、彼が死ぬ直前までやり続けていたことを、まだ25~26歳の時に、既に発言していたというのが凄いですよね。
小池)当時のアートのシーンについては、榎本さんなども発言されていますが、いわゆる現代美術とは異なる日本独特のシーンでしたね。アートもグラフィックも日本独特のうねりの中にあって、その中からいろいろな作家さんが出て来て、谷口さんもその代表的なお一人でした。
津々井)まずは、日比野克彦が出て来て、そのあと、谷口君が出て来て、まさに、藝大旋風みたいな流れでしたね。
伊藤)当時メディアでは、藝大旋風とか芸大パワーと言われていましたね。
津々井)80年代半ばくらいになるとそういった流れが出て来て、一方で、湯村輝彦監修で「イラストレーションピクニック」というイベントをやったりもしていました。
谷口さんと伊藤さんと津々井さんの共通点
編集)先ほど、谷口さんと伊藤さんの作風の共通点についてお話が出ていましたが、イラストレーターの方というのは、脳内のイメージから描き起こすタイプと、目の前のものを模写するタイプがいると思いますが、その辺ではお二人の共通点はあったのでしょうか?伊藤)僕は、基本的に引用やトレースが多いですね。図版や写真に出会ってからイメージが膨らんでいくので、受け身というか。一方で、谷口君は、造形感覚に優れていて、見えないものを形にしていくような、とても描写力のある人でした。
編集)ただ、伊藤さんの作品も基本的にはトレースから始めていても、そこからオリジナリティを発揮しているんで、到着点ではそんなに違いはないような印象を受けます。
伊藤)たしかに、そうですね。
伊藤)谷中のギャラリーで津々井君の個展を見ながら、これまでに気づかなかった3人に共通する「何か」を感じたんです。うまく言葉が出てきませんが、この事について3人で話してみたかったですね。奇しくも谷口君と最後に会ったのが、その日でした。ギャラリーに向かって歩いていたら、個展を見終わった彼と路上でばったり会って、一緒にまた会場に引き返しました。まさか、それが最後になるとは思ってもみなかった。
編集)それは何月の話でしょうか?
津々井)今年の7月頭です。
伊藤)あれ?でも、ちょっと肌寒かった記憶がありますけど。
津々井)雨がずっと降っていたんですよ。
伊藤)僕たち3人の付き合いは長いんですよね。
津々井)正直、これから先も、まだまだ3人の付き合いは続くと思っていました。
伊藤)あの路上での再会が最後だと思うと、なんとも言えない気持ちになります。
日本グラフィック展
小池)ここで話を「日本グラフィック展」あたりに戻してみます。伊藤)谷口君が「グラフィック展」で受賞した作品を見ると、やはり、クレメンテ(フランチェスコ・クレメンテ)※とか、あの辺りの影響を受けているのがよく分かりますよね。
※フランチェスコ・クレメンテ(1952年3月~)は、新表現主義運動に最も密接に関係しているイタリアの芸術家。
谷口君は、この大賞を獲った直後から様々なメディアを通して、すごく精力的に活動し始めたんですよね。似顔絵や人物画、自然の風景画、あるいは、「スタジオ・ヴォイス」の仕事など、いろいろなことに取り組んでいました。
津々井)大賞を獲った後の、谷口君の仕事量というのは半端なかったですよね。ちょうど駒沢公園の花火大会でロンちゃんと会った時に、「谷口君や日比野さんは仕事量が多過ぎるから、こっちにも少し回して貰いたいよね」なんて冗談を言い合っていたくらい凄かったんですよ。それが、ロンちゃんとの初めての出会いでしたね。
伊藤)あれ?その時、初めて会ったんでしたっけ?
津々井)うん、そうですよ。
小池)僕たち世代からしたら、谷口さんや日比野さんなどの諸先輩方の存在を目の辺りにして、「閉塞した世の中の空気を破るような自由な存在が目の前に現れた!」というような感覚を覚えました。そのお陰で、「自分は、これで、いいんだ」と思えるようになったんですよ。ところが、いざ自分自身で取り組んでみると、「谷口さんって、相当に幹が太いな」ということに気付かされました。
伊藤)そうした感覚は、未だにずっと変わらないですよね。同じクライアントと何十年間も続けて来た仕事がいくつもあるのが、彼の凄いところでもあります。
クライアント、アートディレクター、プロデューサーの方々から厚い信頼を得ていましたから。もちろん、作品のクオリティを変わらずにキープする前提があるからこそですが。
榎本了壱さんと一緒にやっていた「おさかなぶっく」(中島水産株式会社)も、その良い例ですよね。
津々井)2001年から20年以上は続けていましたよね。
伊藤)正直言って、ちょっと今、谷口君の代わりになるような人物というのが、思い当たらないんですよ。
津々井)よく考えたら、谷口君という人は、ほんの25~26歳でデビューして、ずっと現役でやって来たんですよね。今のイラストレーターの方々と比べてみたら、想像にも及ばない息の長い世界ですよね。
伊藤)藝大出身で、アカデミックな素養がありましたからね。そのアカデミズムに、イラストレーションの文化的な側面をミックスさせたのが新鮮だったと思います。 それと、いわゆる「ニューペインティング」※のラフでノイジーな要素も、スマートに取り入れていました。
※1980年代に入って盛んになった具象絵画の一傾向。原色を使って、自由で荒々しい筆致で描いており、新自由主義とも言われている。

旅の途中の思し召し
※掲載作品と対談内容は必ずしも一致しておりません。ご了承下さい。
谷口さんの技法
津々井)そういえば、当時、流行していたガムテープを使った「ニューペインティング」と呼ばれるコラージュ的な手法は、すぐに止めてしまいましたよね。編集)そういった表現法は、谷口さんが最初だったんですか?
伊藤)いや、手法としては、色々な人が試していたと思いますが、中でもセンスが突出していましたよね。
小池)谷口さんの場合は、素材が完全に作品に馴染んでいて、単なるアイディアというよりも、素材が作品に昇華されているという感じでした。そういったところが、セツ・モードセミナーの学生たちにも非常に高く評価されていました。
津々井)みんなが谷口君のマネをして、一斉に貼り始めましたからね。
小池)そうした時代の追い風みたいなものと、ご本人が元々持ち合わせているものとが、うまく組み合わさることが重要で、そこが上手くいかないと作家活動は続けられないんじゃないでしょうか。先ほど、伊藤さんも明言されていましたが、それだけ長期的に仕事を継続して行くための資質について、もう一歩踏み込んだご意見を伺えますでしょうか?
津々井)藝大生という括りで言うと、谷口君と日比野君とは学部が異なるんです。谷口君は古美術というか、ちょっと工芸っぽい分野を勉強していて、印刷物の版下なども全て自分で制作できたんです。一方で、日比野君が所属していたデザイン学科の方は、そういうことは余り経験していなかったようです。
そんなわけで、谷口君の方は元々デザインができるという強みもあって、就職先も高島屋の宣伝部だったんです。
伊藤)そうでしたね。
津々井)やはり、デザインができるというのは大きな強みで、自分のことを自分でディレクションしたりもしていたので、新たな仕事の依頼があっても、どういうところで力を発揮すればいいのかという見極めは他の人たちよりも早かったように思いますね。その結果、どこまで自分のわがままを通せるかという、自分なりの駆け引きがきちんと出来ていましたよね。
伊藤)谷口君は、そのあたり絶妙なバランス感覚を持っていたように思いますね。
小池)面白いですよね。アーティストという面だけでなく、仕事人として現場の苦労も理解されていたということですね。谷口さんはイラストレーターでもあるし、アーティストのようでもあるし、さらに、工芸家のような部分も持たれていましたよね。
コンピューター
津々井)たとえば、彼がデザインした手ぬぐいなんかを目にしても、一表現者として、「こんな風なデザインの手ぬぐいにしたいな」というように思い通りに仕上げてしまえる器用な面がありましたからね。 世の中にPCが出て来た時にも、彼は取り入れるのが人一倍早かったんですよ。伊藤)かなり早かったですね。当時のスタッフだった谷田一郎君※の貢献も大きかったと思いますが、とにかく積極的に取り組んでいました。
※1987年ヒロ杉山とNeo-Art-Groupを結成。1994年より3D CGクリエイターとして数々の作品を発表し、1996年にクリエイティブスタジオ「John and Jane Doe Inc.」を設立する。2004年、佐藤可士和氏とART DESIGN を結成し、ショートフィルムを制作。現在はCMを主体として、映像、CG、イラストレーションなどジャンルを問わず幅広く手がけている。
津々井)谷田君は今は映像作家で、監督でしたっけ?
伊藤)そうですね。数々のCMやMVを手掛けて大活躍しました。その谷田君のベースの中には多大な谷口君の影響があると思いますよ。谷口君は、CG作品だけの展示を開催したこともありましたね。
編集)それは何年くらい前の話ですか?
津々井)「銀座グラフィック・ギャラリー」での展覧会は、88年でしたね。
伊藤)なるほど。PCの普及と共にDTPが広まり始めた時期ですね。
津々井)そのPCを使って、ある程度のことが出来るようになったところで、印刷そのものにも拘り始めていましたよね。ただ、出力というところでまだ未知数の部分があったので、PCに作品を取り込んで、レイヤーを上手く使いこなしながら、印刷物にどのように転化して行くかというのが、その頃の彼のテーマだったような気がします。
伊藤)一方で、津々井君は「セレ」というシルクスクリーンの印刷工房を運営していました。そこでは、シルクの特性を生かしたアートブックを作らせてもらいましたよね。
津々井)90年代くらいまでは、個展を開催する度に、「じゃあ、アートブックを作ろう」といって、毎回、製作していましたからね。
編集)津々井さんがその会社を作られたのは、何年頃の話ですか?
伊藤)80年代の半ば過ぎくらいですかね。
津々井)だから、完全に日比野君と谷口君に「おんぶにだっこ」でしたね。あとは、年末になると、ロンちゃんのところの年賀状なんかも請け負っていました。
伊藤)そうでした!年賀状をお願いしていましたよね!
津々井)当時は、オフセットが非常に高額だったんで、「シルクで2~3色で刷れるんで、お仕事ください」と頼んで回って、年賀状の印刷なんかも受注していたんですよ。
編集)世間の人たちが、まだプリントゴッコで懸命に年賀状を刷っていた頃ですよね。
伊藤)まさに、その頃です。僕もプリントゴッコで年賀状を作成したことはありますが、シルクスクリーンにしか出来ないことが色々ありまして。蓄光インクで刷ったこともあるんですが、一見すると、表面上白くて何が書いてあるか分からないんです。ところが、暗いところで見ると、文字が浮かび上がってくるという仕掛けですね。
編集)つまり、夜光性ですか?
伊藤)夜光塗料です。で、結局セレは、いつまで運営していたのでしたっけ?
津々井)おそらく、10年くらい前までやっていたかな。油性インクが使えなくなった時点で、とりあえず、人様のものを刷るのはなるべく断ることにして、たしか、荒井良二さんの作品で最後だったと思います。谷口君の仕事を請け負っていたのも、おそらく90年代くらいまでだったように記憶しています。
小池)谷口さんの交友関係がどんな風に枝葉を分けていいたのか興味が湧いてきますね。
ARCHIVES
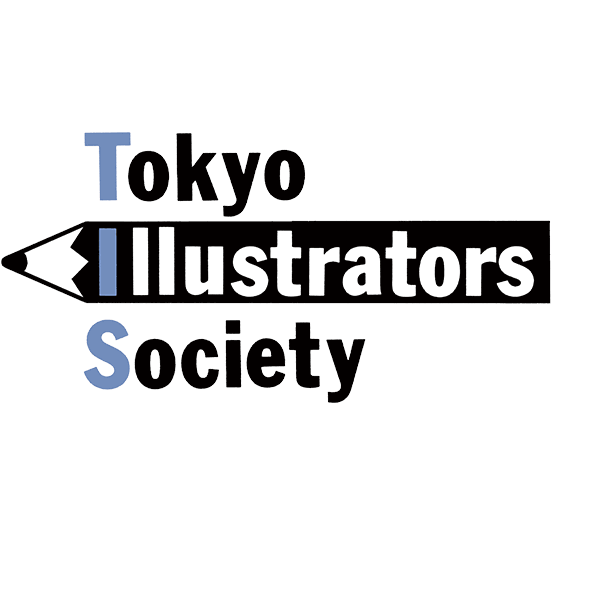




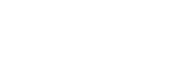

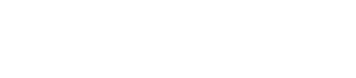
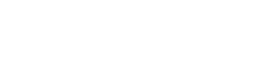




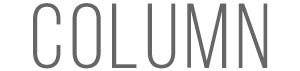
 一覧へ戻る
一覧へ戻る


